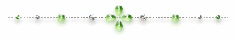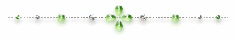
(この人達は何を言っているんだろう……?)
それが僕の正直な感想だった。
見慣れた屋敷の一室で、馴染みのある人々が交わす、聞き慣れない単語。僕はただ、当主様と泰花さんの傍で黙って正座していることしか出来なかった。
いつもの様にお客様をお通しして、去るはずが呼び止められて、話を聴くことになって、30分くらい経つだろうか……そして今に至っているのだけれども……。
「……あの、泰花のお父さん。ちょっと失礼しますね。」
「うむ、如何なされたかな?」
「いえ、今回の主役が隅っこで小さくなってしまっているようですから。……大丈夫?香月くん。」
ふいに名前を呼ばれて、顔を上げる。呼びかけたのは、女性のお客様だった。普通に話を聞いていたつもりだったのだが、お客様は心配そうな微笑みを浮かべていた。
「はい、大丈夫です。ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。」
自分でも何処が大丈夫なんだろうと思ったものの、他に思いつかなかったのでそう答える。
女性は僕の答えを聞くと、まだ少し納得しかねている様子だったものの、再度微笑んで話を戻した。
「それでは、泰花同様、私がお世話をさせて頂きますね。改めてよろしくお願いします。香月くんも、よろしくね。」
「はい、よろしくお願い申し上げます。」
そうして、僕の銀誓館学園への転校が決まった。
それからその日、自室に戻ってから僕は暫く考え事に耽った。学園の寮から帰ってきた泰花さんが話した「雪女」の話と、当主様の話す《能力者》や「銀誓館学園」の話。
(どれも今までは御簾の向こうの話だったというのに……。)
それが突然、春休みになって自分の身の上に降って来た。戸惑わずには居られない。
不意に、過去の記憶が蘇った。
『なにをしているんだ!?』
『やめて、離して!こんな子、私の子じゃない!幽霊よ!出て行け、出て行って!!』
いくつもの、刃物が空を切る音。鋭い痛み。壮年男性の罵声、女性の金切り声。
『あの子、東北からうちに来た子でしょう?礼儀正しくて大人しいのはいいんだけど……あんなに白くちゃ不気味よぉ……。』
『およし、泰花様に聞かれたらお叱りを受けるよっ。ほらほら、仕事なさい。』
日々の雑音に混ざって、ひっそり漂う乾いた声。
『その……香月さんは、ひょっとして雪女一族の方なのではないかと……そう感じたのです、お父様……。』
『香月が、《来訪者》か……成る程。』
不安そうな面持ちの泰花さんと、それきり黙してしまう当主様。
(僕は……僕は、ただの使用人でいいのに……)
そこまで考えて、ふと扉を叩く音がした。
「……あ、はい。」
時計を見やれば夜の20時。こんな時間に誰だろうと思いながら入り口へ向かう。
僕ら使用人の住むのは、土御門の屋敷の離れだ。だから来客があるということは滅多に無いのだ。
そして扉を開けた僕は驚いた。
「えへへ……こんばんは。良かった、お部屋を間違えなくて。」
「まりあ様……!?どうして……」
「んふふ、ちょっと様子が気になってこっそり来ちゃいました♪だから泰花達には秘密なの。」
「それでは、忍び込んでいらしたんですか!?」
「えへへへ……よかったら入れて貰ってもいいかしら?」
まりあ様はいたずらっ子のように笑うと顔の前で手を合わせた。このまま帰ってくれなんて言える筈も無く、急いで部屋へと招き入れてお茶を淹れる。使用人の部屋にある茶葉の質なんて良いものではないが、それしか出せないのでやむをえなかった。
「すみません、粗末なものですが……。」
「あらあら、ありがとうございます。頂きまーす。」
ゆらゆらと湯気が舞う。暫く、静寂が部屋を包んだ。
それから口を開いたのは、まりあ様だった。
「――っあちちっ!?」
「あ、すみません!?あの、失礼しました。大丈夫ですか?熱すぎてしまいましたか……?」
「あ、ううん、いいのいいの。ごめんね、猫舌なものだから油断するといつもこうなの。」
「それなら、良かったですけど……。」
慌てる僕に、まりあ様はばつが悪そうに笑って手を振る。それから一口お茶を飲むと、改めて僕の目を真っ直ぐに見てきた。
「さて。少し緊張は解けてくれたかな?昼間会った時も今も結構がちがちだったけど。」
「……あ。」
参った。すっかり見抜かれていたとは……。
急に恥ずかしくなって俯く僕の傍で、まりあ様はにこりと微笑んだ。
「そんな下を向かないで。それに今、私はお客様じゃなくてあなたに会いに忍び込んできたただの小娘よ。もっと気楽にして頂戴。忍び込んできた甲斐が無いわ。」
「え、ですがまりあ様……。」
「ほーら、その言葉遣い。もっとラフにしてくれていいのよ。せいぜい『まりあさん』くらいでね。私だって普段どおりにさせてもらうわ。」
「はあ……。」
どこまでも奔放な人だ、と思った。突然忍び込んできては僕に会いたいといい、挙句話し方まで指摘してくるとは。
しかしそんな僕の内心を知ってか知らずか、まりあ様――じゃなかった、まりあさんは話を続ける。
「実はね、香月くんと学園に行く前に、一度ゆっくり話しておきたかったの。泰花のときの様に。本当は昼間会えたときにできたら良かったんだけど、あなた忙しそうにすぐ出て行ってしまったから……。」
「そうでしたか。すみません、他の仕事があったものですから。」
「うふふ、やっぱり。私と6歳しか違わないのに勤勉だなーって思いながら後姿見てたのよ。4月からは私も働くんだから、見習わないとなっ。」
「でも、僕なんかより、ちゃんと社会人として働くまりあさんのほうがすごいと思います。僕のは、仕事というよりこれが僕の生活ですし……」
「んーむ、そんな謙遜することないと思うぞ〜? 香月くんだって立派に働いて社会貢献しているんだから。」
僕の言葉をさえぎって、まりあさんが苦笑交じりにそう言った。もっと自信持っていいと思う、と付け足して。
それから暫く学園のことや能力者の話を交わした。一頻り話が終わると、彼女は少し考えるような仕草をした後、改まって話を切り出してきた。
「そうだなぁ……ひとつだけ、お願い事しようかな?香月くんに。いいかな?」
「どういった事ですか?」
「ふふ♪ ちょっとしたことなんだけどね。」
「?」
「うむ……あのですね。」
数度の瞬きのあと、彼女は満面に笑みを湛えて言った。
「いっぱい、笑ってて。気の済むまで泣いて良いし凹んでいいから、その後とか、いつもはいっぱい笑って過ごしてて欲しいんだっ。」
* *
あれから、早いものでもうじき季節が一巡りしようとしている。
まりあさんは相変わらず奔放で、何かにつけ僕の元を風の様に訪れては去っていく。
あの日の「お願い事」は、当時は何故そんなことを言うのかと理解に苦しんだけれど……今は少し、判ってきた気がしている。
(……あれ? そうか、明日は……。)
ふと、目に止まったカレンダーに可愛い花が描かれていた。まりあさんがいつも去り際に残していく、「またこの日に来るね!」のサイン。ふっと笑顔になれる、不思議なサイン。
(お茶とお菓子の準備、しておくか……。)
明日は、彼女の好きな紅茶を淹れてあげようと思った。
------------------------------
あとがき。
------------------------------
ふっと過去作品を振り返れば、泰花の分しか編入時のSSを書いていなかったんです。ということで香月さんのお話を書いてみました。
ただ、ちょっと上手くまとめられなかったんですよね……何度か書き直しをしてみたのですが。
生まれながらの雪女だけど本人も含めて誰もそんなことを知らなくて、色々なものに忍びながら張り詰めて生きてきた香月さん。
その戸惑いとか胸のうちに押し込めたものを、もっと丁寧に描いてあげたかった……まだまだ精進せねばと思い知らされました。
頑張ります!
ではではでは、月城まりあでした。